<所得や資産への「課税」はそもそも「強奪」であり、「累進的課税」はなおさらだ>という見解はどこがまちがっているか? ── 1世紀前、「社会的自由主義者」からの反論
相当な規模になるだろう社会保障の財源を税金から捻出することに関しては、昔から根強い反発、抵抗があり、現代の新自由主義も、この捻出を不当なものとする議論を旺盛に展開している。1980年代以降のアメリカなどで強い影響力を持ってきたのは、新自由主義の最も先鋭な思想的潮流とでも言うべきリバタリアニズム(自由至上主義)であり、彼らは1950年代のF・A・ハイエクらより徹底した議論を展開する。
たとえば、よく知られたリバタリアンの一人、マレー・ロスバードは、徴税は泥棒、場合によっては強盗のやることと同じだと広言し、代表的リバタリアンとして周知のR.ノージックも、多少慎重ながらも、労働による所得に対する課税は強制労働に等しい、貧者の救済のために課税することは悪だ、と言ってはばからない。「再分配」が許容されるのは、暴力・盗み・詐欺からの保護、契約の執行などの最小限度の「警察」的機能への出費に限られ(「最小国家」)、より多く稼いだ人びとから「より多くかすめ取る」という累進課税は、「自己所有権」という権利の侵害であり絶対に許されない、そもそも福祉を求める権利など存在しない、というのがリバタリアンの共通理解であった。
彼らの議論は、自分の労働、自分の努力で築いた富は、あくまで個人的なもの・私的なものであって、社会に何も負っていないという前提にたち、資産や所得(一言で「所有」と称しておこう)に関する課税そのものが本来不当なものであり、福祉国家の「再分配」などを「強制労働」(他人のために余儀なくされる労働)とみなし、課税を少なくとも極小限度にとどめようとする主張である。
さて、新自由主義的ないしリバタリアン的なこうした考え方は、じつは現代に登場した目新しいものというわけではない。そのことは、1世紀前のイギリスの社会的自由主義者L.T.ホブハウスが、その著書『自由主義』の一節で述べた、こうした考え方への反論にうかがうことができる。社会的自由主義は当時「ニュー・リベラリズム」とよばれた、修正自由主義の思想、運動である。ひと言で言えば、貧困を個人責任に帰すことを批判し、社会的責任を分析・承認し、労働組合の権利をみとめて社会政策を広く提案しながら、市場経済をより道徳的に許容できるものへと作り替えて維持しようとする主張であった。ホブハウスのほかに、『帝国主義』を書いたJ・A・ホブソンなどが知られている。
ホブハウスは言う。
相続と遺贈に関する法律によって巨大な不平等が永続する経済システムには、何かしら根本的にまちがったところがあるのではないか。大多数の人びとが自分で稼ぐことができるもの以外は何ももたないまま生まれているのに、一部の人々は、最も能力の優れた一個人がもちうる社会的価値をはるかに超えた分を生まれつきもっているという状態を、私たちは黙認すべきであろうか。
だが、その大多数を占める不運な人びとが要求できる「財源」は何か。ここで税が問題となる。しかし、それは、富裕者たちからは
結局、貧者のために富者が課税されるべきことであり、正義でもなければ慈善でもない、いわば純然たる強奪と言われるであろう。
ここでホブハウスが想定している議論は、現代のリバタリアンの主張そのものである。再分配、社会保障のための財源を税に求めることは強奪に等しい、という声高な抗議がすでに存在していたのである。
「富の社会的基礎」── ホブハウスの反論
対するホブハウスの反論はこうである。
「私は強調したいのだが、富は個人的基礎だけでなく社会的基礎もあわせもつ」。たとえば都市や周辺部の地代の上昇・高騰などは、都市の発展・機能展開にともなう「本質的に社会の創造した」冨の諸形態の一つであって、地主個人の貢献が大きいというものではない。また、「しばしば明瞭に反社会的な傾向」をもつ「金融上や投機的な取引」も富の(特殊な)源泉であるが、個人のまともな「努力」によるものとはとうてい言いがたい。酒類や交通機関などの独占がもたらした利潤も政治・政策的規制がもたらしたものにほかならず、「相続の原理をつうじて、大いに蓄積された財産が次々と継承される」事態についての個人的努力の有無などは言わずもながである。
総じて、これらは「不労所得」と言うべきものであり、個人の特別な「努力」や「貢献」とは本質的に無関係であろう。これらの財産・富は「本質的に、各人が自分自身の労働の果実を自分に確保できる制度であることをやめ」、「他人の労働を支配できる道具となっているものである」。
問題の核心はどこにあるか。
そもそも、富・財産とは、一人の個人で築けるようなものではなく、社会的基礎をもっている。第一に、たとえば、「まったく独力で身代を築いたと考えている成功した実業家」といえども、秩序や安全の確保、産業の発達を可能にする社会的インフラ(道路や鉄道・海運、水道等々)の整備、文明の英知・科学と産業の集団的成果としての諸発明、熟練労働者大衆の存在、生産物への需要その他がなければ、みずからの財をなすことなどとうてい不可能である。
そして第二に、大規模な分業にもとづく大工業生産を基幹とする近代産業は、共同労働、つまり計画的・組織的な集団労働という意味での社会的労働によって成り立つものである。そのように、
年々生産される富の大部分が社会に起源をもつと考えるのが正しいならば、この〔諸個人への〕報酬の割当ての後に余剰が残るであろうが、その余剰こそは、共同社会の金庫に入り、公共の諸目的のために、……役立つべきものなのである。
つまり、一見、個人の所有物に見えるものも含めて、富の大きな部分、富を作りだす基礎の大部分は、じつは共同社会に帰すべきもの、「社会的財産」(あるいは「社会的相続財」)である。そして、協働(分業―協業)が余儀なくされる「近代産業においては、個人が助力なしの独力でなしうることはきわめて少ない」。
税=社会的財産の共同社会の金庫への回収
そうである以上、一般に大きな所得にかんして、高度の累進課税や大幅な付加税などによって、多額の課税をすることには十分な理由がある。実業家個人の貢献に属する部分は実業家の報酬であってよいのだが、それは、他の個人の富の生産への貢献とくらべてそれほど多いはずはないからである。生産された富のうちの個人的報酬として妥当な分を除いた部分が社会的富、社会的財産である。「再分配」の基礎はこの「社会的財産」であり、それは徴税によって、社会の「共同の金庫」に回収されるべきものである。(なお、個人の貢献への報酬の妥当性は、諸個人の能力が十分に発揮されるような刺激を与えられる報酬かどうかによって決まる。報酬の最高限度を5000ポンドにしても、原理的にはそうした制度設計への努力は可能だという。)
少し立ち入ってホブハウスの言葉を聞こう。
自由党は「どんな源泉から生じたものであれ、高額所得には高額所得付加税を課す」と主張しているが、この課税原理は「ただ一人の個人は、はたして幾人かの個人がじっさいに獲得している分と同じ程度に、社会にとって価値があると言えるのかどうか」(一人の人間の貢献が何人も貢献の合計を上回ることがあるのか)という疑問を根本原理としたものである。
「個人がもちうる産業的価値のおおよその限界」(一人が働き出しうる限度)を超える所得に対して
急激な累進課税をかけても、真に社会的な価値のある何らかの事業を妨げるということはありそうもない。よりありそうなのは、法外な富をえようとか、社会的な権力をえようとか、見せびらかしの虚栄といった反社会的な情熱を砕くだろうということである。
こうして
税制の真の機能は、その起源を社会にもつ富の要素を社会のために確保すること、あるいは、もっと広く言えば、その起源を現存する個人の努力に負うことのない一切のものを、社会のために確保することである。
この原理にもとづく課税は、リバタリアンが論難するような「ポールに支払うためにピーターから奪い取る」というケースではない。
ピーターは奪い取られるのではない。むしろ税は別として、国家から奪い取っている者こそ、ピーターである。社会的な価値をもつ一定の取り分を国家が確保できるようにする税は、納税者が自分自身のものであり無制限の権利をもつと主張する何ものかから由来するのではなく、むしろはじめから当然社会に与えられるべきものの払い戻しなのである。
「社会的財産の共同社会の金庫への回収」、これこそが徴税の原理だとホブハウスは言う。これは、新自由主義・リバタリアニズムが主張する「福祉国家の財源・再分配=税の強奪」論に対する、1世紀を遡っての「社会的自由主義者」の回答である。
(引用はL.T.ホブハウス『自由主義』監訳 吉崎祥司 訳 社会的自由主義研究会、大月書店、2010年から)
吉崎祥司(北海道教育大学名誉教授)
 L.T.ホブハウス『自由主義』監訳 吉崎祥司 訳 社会的自由主義研究会、大月書店、2010年
L.T.ホブハウス『自由主義』監訳 吉崎祥司 訳 社会的自由主義研究会、大月書店、2010年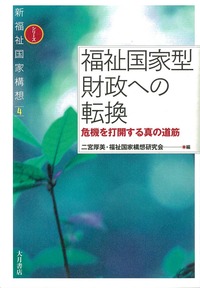 二宮厚美・福祉国家構想研究会編『シリーズ新福祉国家構想4 福祉国家型財政への転換』大月書店、2013年
二宮厚美・福祉国家構想研究会編『シリーズ新福祉国家構想4 福祉国家型財政への転換』大月書店、2013年
